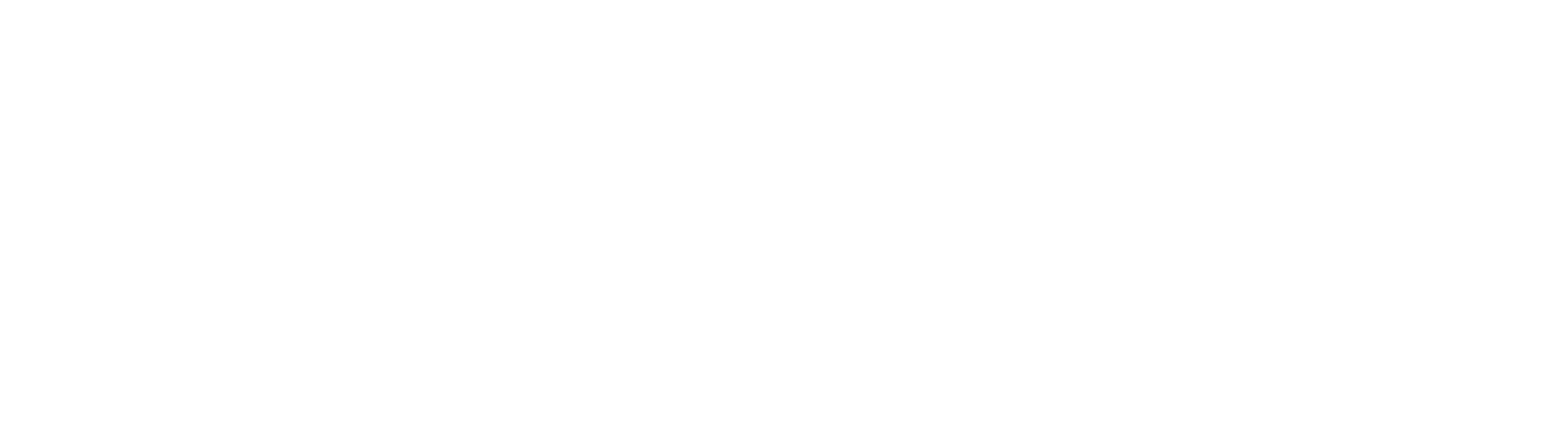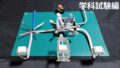2025年上期の第二種電気工事士試験に一発合格できたので自分なりの手順やノウハウを紹介します。
本記事では「導入編」と題し、試験の受験に至った経緯や試験の概要などの情報を紹介します。
学科試験については「学科試験編」を、技能試験については「技能試験編<前編>」「技能試験編<後編>」をご参照ください。
- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(導入編)(本記事)
- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(学科試験編)
- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<前編>)
- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<後編>)
目次
背景(受験の動機)
持ち家の電気まわりの状況
我が家は中古で購入&築30年近くの家なので電気まわりのいろんなものが最近の仕様ではなく、また自分好みの仕様にできていない箇所が多くあります。
例えば、照明とコンセントは次のような感じです。
照明
今後の金銭コストを下げるために「照明が故障や球切れしたときにはできる限り自分で交換できるようにしたい」という思いがあったので、家を購入直後に各所の照明を施工してもらう際に「蛍光灯とLEDのどちらにするか」「なるだけシーリングにする」などを考えて照明を取り付けや施工してもらいました。
しかし、玉替えできる照明にしたり、シーリング化できたところもある一方で、「既存の直付けの照明」や「新規取り付けしたけど直付けしか選べなかったもの」があり、直付け照明が家の中にいくつか残ってしまいました。

コンセント
コンセントは、すべて2口(ふたくち)です。

できたら自分でメンテしたい(でも資格が必要)
家が上述のような状況であるので、照明器具や設備が古いので随時それらの不具合が出てくるだろうし、玉交換や器具交換だけでなく電気工事の施工が必要になってくる箇所もあります。
その他、快適にカスタマイズしていきたくもあります。
でも、直付けの照明やコンセントの電気工事の施工には資格が必要なため、業者に施工をお願いする金銭コストも手間コストも大きくて、もったいないしめんどい。
ということで、『将来的に電気工事士の資格をとって自分で施工できるようになりたい』と考えていました。
大学で電気工学を専攻していたので、電気知識ゼロベースの人よりも資格取得も少し敷居が低いはずとの胸算用も。
なのですが、多忙だったり受験が億劫だったりと資格取得は先延ばしになっていました。
2027年に蛍光灯の製造終了!
そんな中、「2027年末までに蛍光灯の製造・輸出入が終了」との情報が各所で流れるようになりました。
すなわち、2028年以降は自分ちに残っている直付けの蛍光灯照明は球切れであっても実質取り換えが必要になるということになるわけで、「照明故障時のコスト増」のタイムリミットが直近にせまってきているということになりました。
思い立ったが吉日(受験を決意)
という流れがあり
↓
きっかけをもらったこのタイミングを逃すとまた先延ばしになりそうだ
昨今自身の脳の劣化も著しい
↓
この機会に受験してしまおう!
と2025年の第二種電気工事士の受験を決意しました(このとき2024年秋冬)。
以降の解説の前提(自分が持ってる知識とか)
受験者である筆者が「どういう知識をベースとしているのか」とかの前提を以下に記しておきます。
この情報をもとに、以降の文章を読んでいただく際に情報の取捨選択をしていただけたら幸いです。
- 大学と大学院は電気工学を専攻&修了(1990年代)なのでゼロベースの人よりはアドバンテージあり。
- しかし、研究室も仕事もずっと情報系メインだったので授業で習った知識しかない&勉強したことはほぼ忘れている(勉強してから30年以上経過)。
- 「三相交流」とかは「送電とかの勉強やったなー」ぐらいで初見の人よりアレルギーがないぐらいの程度。
- 「接地」「電位」という概念が理解できているのでそこはアドバンテージあり(回路の計算問題や複線図描くのとかは比較的得意)。
- 趣味レベルで自分で車やバイクの電装系をいじってきた経験があるので「接続」「ストリップ」「工具の操作」などは馴染みがあるし不得意ではない。
- 今回学科試験の勉強をしてみたら、ケーブルとか工具の種類とか「いやちょっと待って」というぐらいさっぱりわからず最初はだいぶ焦った。
第二種電気工事士について
受験することに決めた「第二種電気工事士」について少し解説してみます。
第二種電気工事士とは
第二種電気工事士は国家資格です。
ここでは、「電気工事士」や「第二種電気工事士」とはどういうものかについて記載されているWebサイト(以下)を紹介しておきます。
各公式サイトの情報をご参照いただき、ここでは説明は省略させていただきます。
電気工事は資格が必要!
先でも少し触れましたが、以下のような電気工事を行う際には電気工事関連の資格を持っている(正確には免状を保持している)必要があります。
- 家のコンセントを2口から3口に変更
- 家の直付け配線の照明を照明器具ごと取り換える
「第二種電気工事士」はこういうのを施工するための資格の中で最も容易に取得できる(試験に合格できる)資格だと思います。
なお、商売として電気工事を行うためには別途「登録」などの手続きが必要で、免状を持っているからどんな電気工事もやってよいわけではありません。
「どこからが法令違反?」ということについては後述にて詳細を解説しています。
試験の概要
第二種電気工事士の免状を取得するためには、資格試験に合格する必要があります。
第二種電気工事士の資格試験は「学科試験」(筆記試験)と「技能試験」(実技試験)の2つの試験で構成されており、毎年度「上期」「下期」の計2回実施されています(2025年時点)。
第二種電気工事士試験は国家資格の中では比較的合格率が高めな試験みたいです。
以降で、試験の概要や流れなどを紹介したいと思います。
正確な情報は、以下の公式サイトの情報をご参照&ご確認ください。
試験の流れ
第二種電気工事士の受験および免状取得の流れを以下に紹介しておきます。
今後、試験の仕組みが変更になるかもしれないのでご参考まで。
-
申込受験申込
- 費用を支払う。
- 学科試験および技能試験の試験地を指定する。試験地は一定期間変更可能。
-
CBT方式への切替申請(学科試験をCBT方式で受験する場合のみ)
- 受験申込後しばらくたったら申請可能になる。
-
学科試験学科試験を受験
- CBT方式の試験日は自身の指定日。
- 筆記方式の試験日は定められた固定日。
-
学科試験の結果発表
- 合格なら技能試験を受験できる。
- 不合格ならここで終了。
-
技能試験技能試験を受験
- 試験日は定められた固定日(試験地依存)。
-
技能試験の結果発表
- 合格なら免状交付申請できる。
- 不合格ならここで終了。申請すれば翌年の同じ期まで学科試験免除される。
-
免状取得免状交付申請
- 役場役所にて都道府県知事に申請する。
-
免状交付
試験の内容
この記事では試験の内容については省略します。「学科試験編」「技能試験編」にて紹介しますのでそちらをご参照ください。
2025年度の第二種電気工事士試験を受験してみた
実際に、2025年度の上期の第二種電気工事士試験に申し込んで受験しました。
該上期試験の公表されている試験日程は以下の通りです(受付および試験は終了しています)。
2025年度の上期の試験日程
- 受験申込受付期間
- 2025/3/17~4/7
- 学科試験のCBT方式への変更期間
- 2025/4/11~4/17
- 「試験地」と「受験票の記載事項」の変更期限
- 学科試験
- 2025/4/17
- 技能試験
- 2025/5/30
- 学科試験
- 試験日
- 学科試験
- CBT方式:2025/4/21~5/8
- 筆記方式:2025/5/25
- 技能試験
- 2025/7/19 or 7/20
- 学科試験
- 受験手数料
- 9,300円(インターネット申込)
- 9,600円(郵送書面申込)
出典:第二種電気工事士試験 – 電気工事士 – 一般財団法人 電気技術者試験センター
受験申込
「第二種電気工事士」の受験申込をすると、「学科試験」と「技能試験」の両方を合わせた受験申込を行ったことになります。「学科試験」と「技能試験」を一括して申し込み、「学科試験」に受かった人だけ「技能試験」を受験できるという仕組みです。
自分は電気技術者試験センターの公式サイトから申し込みました。
アカウントを作成して、マイページから申込処理を行います。
ほっとくと忘れそうなので受付期間の初日(2025/3/17)に行いました。
受験申込に必要なもの
マイページからの受験申込の際に本人確認用の「顔写真の画像」のアップロードが必要になります。
自分は自宅屋内の壁の前でカメラで自撮りしたものを「顔写真の画像」として使いました。
受験申込の内容(自分の例)
自分が受験申込したときの申し込み内容は以下の通りです。
- 学科試験の試験地
- 和歌山(受験申込時は「大阪」にしていたが後日変更)
- 技能試験の試験地
- 和歌山(受験申込時は「大阪」にしていたが後日変更)
- 学科試験の方式
- CBT方式(受験申込後に後日変更申請)
試験地とは
学科試験および技能試験の「試験地」は「どの都道府県の試験会場で試験を受けるか」を指定するものです。
実際に試験を受ける「試験会場」は指定できません(試験センターによって固定で割り振られます)。
CBT方式で受験する学科試験は、CBT方式への切替申請時に試験会場を指定できます(というより自分で「日時」と「会場」を選択して予約する必要があります)。
過去の実際の試験会場の情報を公開してくださっているWebサイトがありましたので参考にされるとよいと思います。
受験の準備で最初にやったことと反省点
結論から述べますと、声を大にして言いたいのは
「まずはスケジュールをベースに全体像を理解したほうがよい」
ということです。
具体的には
「どの順番で何をどの時期から着手していくかをちゃんと整理して対策や準備していくべき」
と自分は感じました。後述の反省点がもとになっています。
以下は、自分が実際「さあ試験に臨もう」と思ってまずざくっとネットで情報を検索した結果「どんなことがわかったか」について羅列したものです。
- ノウハウなどの情報を紹介しているWebサイトや動画がある。
- 学科試験と技能試験があって最初は学科試験から受験する。
- 技能試験では指定工具を自前で揃えて持っていって試験会場で工作する必要がある。
- 学科試験用の勉強をするための書籍が出版されている。
- 学科試験の過去問題は書籍もあるし、公式サイトからも無料入手可能。
- 技能試験用の練習をするための部材が販売されている。
ここからは反省点の話ですが、2024年末頃にネット通販で「どんなんがあるかな」ぐらいの気持ちで工具と部材を見てたら、「工具と2回分部材と書籍がセットになったキット」がセールになっていました。
「試験直前になったら品薄になったり高くなったりするかもしれないから先行して買っておこう」と思い立ち、それ以上深く考えずに商品を購入しました。
しかし、試験勉強する段階になって「年ごとに試験に合わせて部材が変わる可能性がある」ことを知り、「この時期にこのキットを入手するのは得策ではない」ことがわかりました。たまたま部材が2024年と2025年で同じだったのでセーフでしたが、軽率な行動だったと反省した次第です。
ということで、文頭に書いた結論に至っています。
なお、受験の準備の詳細については「学科試験編」「技能試験編」で詳しく紹介したいと思います。
どこからが法令違反?
将来的に免状を取得して電気工事を行っていくにあたって、それまでに「どこまでやってよいのか」「どこからが法令違反なのか」をちゃんと理解しておかないといけないので真面目に調べてみました。
法令および法令に付随する文書
まずは、調べた「法令」関連のソースを以下に記します。
- 電気工事士法
- 電気工事業法(正式名称:電気工事業の業務の適正化に関する法律)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律 告示・内規等
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の逐条解説(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/koujigyouhouchikujyou.pdf)
法令の理解において重要と思ったポイント
上述の法令や文書を熟読した結果、「違反か否か」のラインについてロジカルに(表などで)表現するのは難しいと感じました。
また、不明瞭な情報やミスリードを誘発する情報を書くのはよくないと思いましたので、ここでは筆者が法令の理解において重要と思ったポイントをピックアップするのみとしました。
ここに記載した情報も鵜呑みにはせず、正確な情報は各法令の条文や公的文書などをご参照お願いします。
- 「電気工事士」は電気工事を行うことができる資格だけど、電気工事の欠陥によって災害を起こしたりすることがないように厳重に注意して施工しなければならない。
- 「電気工事士法」第一条、第五条1より
- 「電気工事業」を営むためには「登録電気工事業者の登録」または「通知電気工事業者の通知」が必要。
- 「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第三条、第十七条の二より
- 「電気工事業者」とは「登録電気工事業者」および「通知電気工事業者」をいう。
- 「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第二条より
- 「電気工事業」とは他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償の行為を問わない。
- 「電気工事業の業務の適正化に関する法律の逐条解説」p.4より
- 「電気工事業」に含まれるか否かに係わらず電気工事の作業は電気工事士法に基づき電気工事士が行う必要がある。
- 「電気工事業の業務の適正化に関する法律の逐条解説」p.5より
出典:電気工事法|e-Gov法令検索
出典:電気工事業の業務の適正化に関する法律|e-Gov法令検索
出典:電気工事業の業務の適正化に関する法律の逐条解説(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/koujigyouhouchikujyou.pdf)
電気工事業者でなくても施工可能なケース
なお、「電気工事業の業務の適正化に関する法律の逐条解説」には、「電気工事業者」でなくても施工可能なケースについて記載があります。一部を以下に抜粋しておきます。
家庭用電気機械器具の販売業者が、電気機械器具(テレビジョン受信機、電気ストーブ、電気洗濯機等の機器)の販売に伴って、例えばその機器用のコンセントを設ける等の配線工事を局部的に行うことが消費者サービス上一般化している場合があること、家庭用電気機械器具の販売に伴う消費者への便宜を図ること等を考慮して、この法律でいう電気工事の範囲から除外し、電気工事業の登録を受けていない家庭用電気機械器具販売者であっても、電気工事士が、その作業に従事する場合であれば、これを行い得る
他の者から依頼を受けないで電気工事を行う場合(例えば、電気工事士の免状を有する者が、たまたま自宅の電気工事を行う場合等)や、試験的、一時的に電気工事を行う場合等は含まれないと解釈されている
ビル管理業者がそのビル管理の必要上当該ビル内の電気工事を自らが反復・継続して行っている場合であっても、これは電気工事業には該当しないが他の者から依頼を受けて電気工事を行う部分が含まれればこの限りではないと解釈される
他の業をもつ者がたまたま1回限り電気工事を行う場合や、住宅メーカーが、自らがアフターサービスとして一時的に行うコンセントやスイッチの取り替え(造営材に取り付けてある配線器具の不具合による交換であって、新設や移設、増設を含まない)についても、電気工事業には該当しないと解釈されるが、当該作業は電気工事士法に基づき電気工事士が行う必要がある
出典:電気工事業の業務の適正化に関する法律の逐条解説(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/koujigyouhouchikujyou.pdf)pp.4-5
自宅の電気工事の捉え方
これまでに紹介してきた情報から「自宅の電気工事」に関して以下のことがいえると思います。
- 免状を有していれば自宅の電気工事を行うことができると解釈してよい。
- だからといって、安易に作業してよいものではなく、厳重に注意して施工する必要がある。
- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(導入編)(本記事)
- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(学科試験編)
- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<前編>)
- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<後編>)